|
||
 |
||
    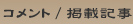 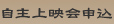   |
  |
|
   |
2005年2月1日号 WEB
筆者 WEB編集部 オッチョ WHOの報告では、世界のエイズ感染者は5000万人に達したという。タイでは1984年に最初のエイズ感染者が見つかって以来、現在までにタイ全国で約130万人が感染したと推計されている。 先日開かれたバンコク国際映画祭において、日本人の女性監督によるエイズ患者を取り上げたドキュメンタリー映画が上映された。そのタイトルは”Yesterday Today Tomorrow”。撮影に三年、編集に一年という長い時間をかけてついに今回の上映へと至った。 映画の舞台はタイ北部のパヤオ県。エイズ禍の深刻なタイにおいてパヤオ県はもっともエイズの患者密度が高く、10万人あたり約1600人という統計が出ている。パヤオ県は他県や他国への出稼ぎ労働者が多く、その出稼ぎ先でエイズに感染し、自分の感染に気付かぬままにパヤオ県に帰り広めてしまっているのだという。 映画はとある夫婦が脱穀の作業に勤しむシーンから始まる。この映画の主人公のひとりであるアンナとその夫のポムである。アンナは前の夫からエイズに感染し、夫を亡くしてから同じくエイズ感染者のポムと出会い結婚した。 「社会に何か強い提唱を投げかけるような作品ではない。価値観を押し付けるようなことはせず、この映画を見て何を感じるかは見る人に任せるようにした」 この映画の監督である直井里予さんの言葉である。作品中、ナレーションは入らず、音楽も入らない。ときおりインタビューだけを交えながら、彼らエイズ感染者たちの淡々とした日常生活をカメラは静かに追ってゆく。 エイズ患者というと、人生に絶望し廃人のようになりながら死が訪れるのを待つというようなイメージが一般的にあるのではないだろうか。しかしこの映画に登場するエイズ患者たちはそのイメージとはあまりにもかけ離れている。 彼らは畑を耕し、川で水遊びをし、ギターを弾いて歌い、そして無邪気に笑う。そこには陰気さのようなものは少しも感じられない。もちろんその内面には、他の人間には推し量ることのできないような不安や悩みや恐怖を抱えているのだろう。しかし死というものをすぐ間近にリアルに感じている彼らは、今のこの瞬間を生きることを大切にし、その生は他の人間よりもひときわ輝いているように見える。 エイズ患者に限らず死というものはすべての人間に訪れるものなのだけれど、ほとんどの人間はそこから目をそむけ、そんなものはないかのように振る舞い、自分の生が永遠に続くかのように錯覚してしまう。しかし生と死はコインの裏と表のようなものであり、死から逃げずに真正面から向き合ってこそ生の部分も充実してくるのではないだろうか。残された時間のわずかなエイズ感染者たちはいやがうえにも死と向き合わねばならず、そこには退屈な日常などというものは存在しないのだ。 この映画は、しかしエイズ患者たちの明の部分のみを描いているわけではない。 映画の終盤において、映画患者であり映画の主人公のひとりであるボーイという少年の入院生活を撮ったシーンがある。映画の前半においては無邪気に走り回り元気な姿を見せていたのだが、病状は進み頬は痩け手足は棒のように痩せ細っている。エイズという病気がいかに悲惨であるかがダイレクトに伝わる。それでもベッドの上で誕生日プレゼントの腕時計を受け取ると、顔をほころばせて喜んだ。この映画に登場した主人公たちの中で、唯一彼だけが作品の完成を待たずして亡くなってしまった。 現在のところ、エイズの特効薬というものはない。いくつもの治療薬が開発されているが、それによってエイズが根本的に治るということはない。しかしHIVウイルスを全部駆逐することはできないものの、かなりの長期に渡ってその増殖を防ぎ、エイズの発症を抑えることのできる薬は開発された。これはエイズに感染したからといってすぐに死につながるわけではなくなったということを示している。タイ政府はかなりの量のこの薬を国民に無料で配布しているという。 しかしこの薬が国民に浸透することは、エイズへの危機感が薄まることにも繋がりかけない。薬よりもまずコンドームを無料配付する方が先なのではないか。 僕のそんな意見を監督に向けると、監督は深く頷いた。 |
| ▲このページのTOPへ | |

Khong Rithdee(コン・リスディー)
――ドキュメンタリ・フィルム「昨日 今日 そして明日へ・・・」―――
直井里予の心に響くドキュメンタリー「昨日 今日 そして明日へ・・・」の中の一場面で,北タイのHIV陽性の父親が病床の、やはりHIV陽性の11歳の息子を慰めようとして、お前はやがて死ぬけれど悲しまなくてよいのだと理由を説明している。
「お前はもう世の中を十分見てきただろう。バンコクにも行ったし、飛行機にも乗ったし、おいしいものをたくさん食べたし、たくさん遊んだし」。「世の中にはそういうことをする機会もなくて死んでしまう人がたくさんいるんだよ」、と。
父親にとっても息子にとってもつらいことではあるが、しかし、これ以外の言い方があるだろうか? 息子が死ぬことについて父親が息子に話すのは残酷だろうか?
我々にとってはたぶん答えはyesだろう。我々にとってHIVは同情を直ちに呼び起こすおそるべき3文字略語なのだから。しかし彼らにとっては、この静かなあるがままに見据えたドキュメンタリーが示すように、HIV感染とは生きることの現実であり、時々刻々をそれとともに生きなければならないものであり、それとどう向かい合うべきかなどと考えている暇はないのである。父親の率直な言葉は残酷ではないが、しかし悲しいものではある。なぜならその言葉は息子にではなく、彼自身にもむけているからだ。
「お前はやがて死ぬ.そしてまもなくお母さんもおれも死ぬんだよ」と彼はいう。
里予は日本のジャーナリストで、1999年からタイに住んでおり、3年を費やしてタイ北部の田舎のHIV陽性の2家族の生活を記録してきた。その成果がこの無駄のない、時折無邪気さをみせる心を動かすドキュメンタリーなのである。
里予はくどくど説明しないし、HIV/Aidsが大問題であることをいまさら解説したりする必要はまったくないというスタンスを採っている。彼女の映画は主役たちの毎日の生活とストーリーをただ示すだけであり、それだけでこの病気が人の感情や生活に与える影響を十二分に物語っている。
最初に出てくる家族はアンナとポムの夫婦である。二人とも農民でHIV陽性である。アンナは最初の夫を1998年にHIV関連の病気で失ない、数年後にポムと再婚した。ポムも同様にHIV陽性の最初の妻を失っている。もうひとつの家族は父親のアチュン、母親のスパニ、そしてボーイとよばれる11歳の息子の3人家族である。3人ともウイルスに侵されているのだが、スパニが目に見えて病んだときも、ボーイが入院したときも、平然と農業を続けている。
あえて比較を強いることなくこのフィルムは両家族の対照的な運命を示してくれる。アンナとポムの取り扱いでは二人がたえず自分たちの状態を意識しつつも暮らしを進めてゆこうとする意欲を読み取ることができ、全体的には事態を客観的に捉えている様子を感得することができる。一方アチュン一家については、とくに映画の前半で父親の農園で大きなジャックフルーツの収穫を楽しそうに手伝っていた陽気な少年ボーイが、やがてやせ細り、病床に伏すようになる経過を見るとき、暗黒雲が覆ってゆく。しかしここでも強く印象に残るのは少年の病気のことではなくて、むしろ親たちの冷静で賢い反応のことである。
こうしてみると「昨日 今日 そして明日へ・・・」を世の多くのエイズ関係の映画のように人生を一変させる悲劇についての涙を誘う類のフィルムと思ったら大きな間違いである(それはそれで映画としての価値があるけれど)。両家族とも特に貧しくもなければ、とりわけに絶望的でもない。彼らを受け入れ、支えてくれる社会の中で淡々と暮らし続けるだけである。フィルムはつねに距離を置いた観察をするというスタイルを保つのだが、折に触れてさりげなくスタイルを変えて対象に近づいて探りを入れる。
もしあなたがこの映画をみて泣くとすれば(じっさい、たぶん泣くでしょうが)、それは主役たちをかわいそうに思って泣くのではなく、彼らがしたり、言ったりすることのすべてがいかにももっともであることが理解でき、またそれ以外には選択の余地がないのだというあまりに痛ましい事実に気づいて泣くのである。
里予はバンコクを本拠地とし、撮影と編集のほとんどすべてを自分ひとりでやったという。彼女の打ち込みようは「昨日 今日 そして明日へ・・・」の粘り強く、考え抜かれた進め方によく現れている。里予は独力でフィルムを仕上げるために祖母と両親がお金を貸してくれたという。提供者である彼らはそのことを大いに誇りに思ってよいだろう。
(和訳 新山英輔)