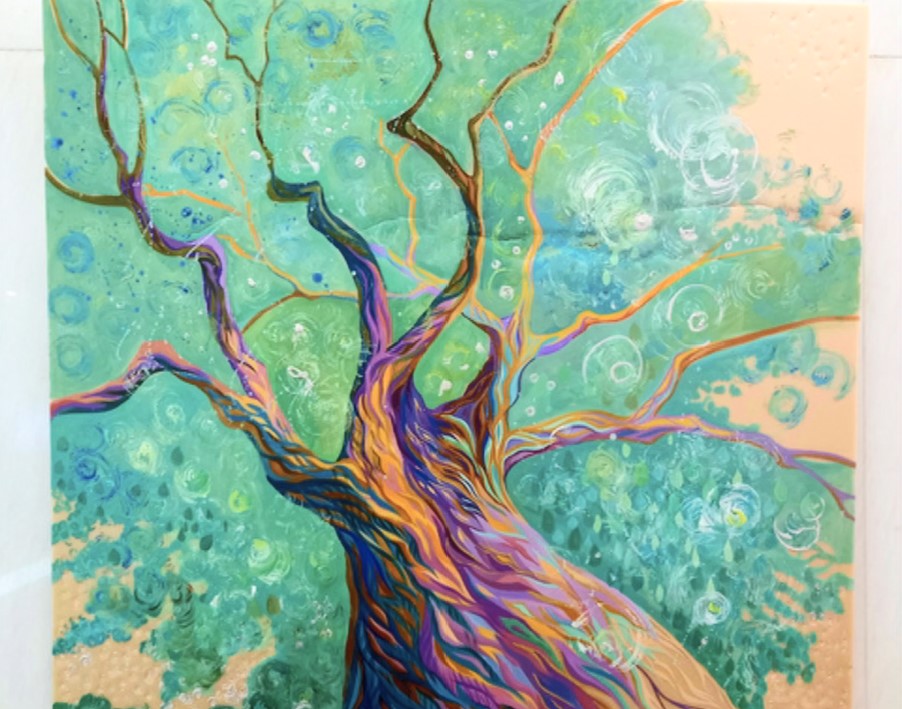同志社大学グローバル地域文化学部
About Project
同志社大学グローバル地域文化学部が2022年度に開講した「グローバル地域文化学の実践4(多文化×映像フィールドワーク)」では、学生が京都における多文化の日常をテーマとした短編ドキュメンタリー映画を制作しています。本授業は、学生が、地域の現場に足を運び、映像を用いたフィールドワークと制作(撮影・編集・上映)を通して、自己を批判的に見つめなおし、多文化な地域社会へアプローチするための共感力と発信力を身につけることを目的としています。文化も価値観も違う他者をいかに理解し、どのような関係性を築いていくことができるでしょうか?
作品を上映し、対話を通じて開かれたコミュニティや共生社会の在り方についても考えていきます。
*参考HP:2019年度プロジェクト科目「グローバルビレッジを撮る・観る・創る―ドキュメンタリー映画制作を通して見つめる京のムスリムと多文化共生」http://riporipo.com/doshisha-pbs/
最新情報 2025年1月9日HP更新NEW!
- 2025.1.09 同志社大学での上映会(1月10日)@寒梅館の開催が決定しました(内部上映)。
- 2024.2.14 「古木を抱きしめて」が京都大学東南アジア地域研究研究所「映像で学ぶ東南アジアの文化と社会」主催の上映会(3月29日)で上映されます。
- 2023.2.17 「ウクライナから京都へ~今 できること」が京都大学東南アジア地域研究研究所「映像で学ぶ東南アジアの文化と社会」主催の上映会(2月24日)で上映されます(無事、終了しました!)。
- 2023.2.10 「ウクライナから京都へ~今 できること」がオンラインシンポジウム「いま、『避難』を考える 避難現場での支援と助け合いのあり方」(2月18日)で上映されます(無事、終了しました)。
- 2023.1.21 同志社大学での上映会(1月20日)は、無事終了しました。
- 2022.12.23 同志社大学での上映会(1月20日)の開催が決定しました。
- 2022.12.23 HPを公開しました。